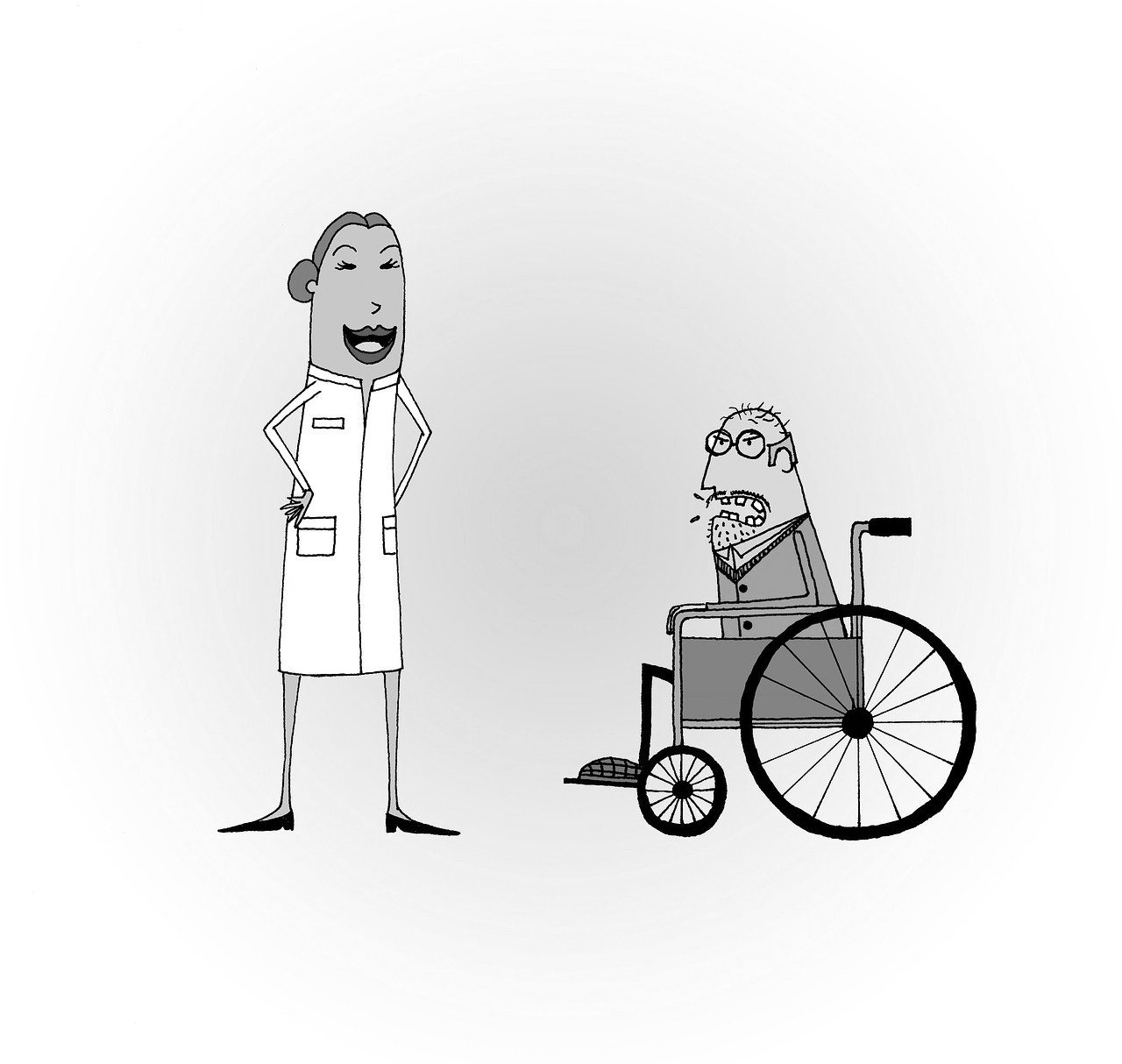こんにちは、KAIGO KAKUMEIです。今回は介護保険制度におけるお金の流れを分かりやすくお伝え出来たらいいなと思います。
介護保険制度って聞いたことはあるけど、「誰が払って、誰がもらってるの?」と聞かれると、ちょっと曖昧かな…という方も多いのではないでしょうか。今回の記事では、介護保険制度の「お金の流れ」について、できるだけわかりやすく解説します。将来の備えとしても、家族のためにも、ぜひ知っておきたい内容です。
介護保険って何のためにあるの?
介護保険制度は、2000年に運用スタートした「みんなで支える介護の仕組み」です。高齢になって介護が必要になったとき、誰もが安心して介護保険サービスを受けられるように、国民全体で支え合う制度です。
たとえば、通所介護(デイサービス)や訪問介護(ホームヘルプサービス)、特別養護老人ホームなどの介護保険サービスを受けるとき、介護保険があることで費用の大部分をカバーしてもらえます。これがなかったら、月に何十万円もかかることもあるので、制度の存在はありがたいものです。
お金の出どころ:誰が払っているの?
介護保険のお金は、主に「保険料」と「税金」の2つから成り立っています。
① 保険料を払う人たち
介護保険料を支払うのは、40歳以上の人たちです。年齢によって2つのグループに分かれています。
- 第1号被保険者(65歳以上)
→ 年金から保険料が差し引かれます。 - 第2号被保険者(40〜64歳)
→ 給料から天引きされる形で支払います。
つまり、40歳を過ぎると、”介護保険が自身に必要となった時のため”に月々介護保険料をおさめることが義務付けられるということです。
② 税金も使われている
保険料だけでは足りないので、国・都道府県・市町村が税金で補助しています。ざっくり言うと、介護保険の財源の約半分は保険料、残りの半分は税金です。
【内訳】
税金(公費): 約50%
国:25%
都道府県:12.5%
市区町村:12.5%
保険料: 約50%
第1号被保険者(65歳以上)の保険料:約23%
第2号被保険者(40〜64歳の医療保険加入者)の保険料:約27%)
お金の使い道:誰がもらっているの?
では、その集めたお金は誰に使われるのでしょうか?
介護保険のサービスを受けられるのは、「要介護認定」を受けた人です。市町村に申請して、介護が必要と判断された人が対象となります。
サービスを利用するとき、利用者は費用の一部(原則1割〜3割)を自己負担し、残りは介護保険から支払われます。たとえば、10万円のサービスを受けた場合、自己負担は1〜3万円で済み、残りは保険から事業者に支払われる仕組みです。
もし介護保険がなかったら…?
介護保険がなかったら、介護サービスの費用は全額自己負担になります。たとえば、特別養護老人ホームに入所すると、月に20〜30万円以上かかることもあります。訪問介護やデイサービスも、毎回数千円〜数万円の負担になるでしょう。
そう考えると、介護保険制度があることで、経済的な負担が大きく軽減されていることがわかります。
まとめ:介護保険は「みんなで支える仕組み」
介護保険制度は、自身が使うときだけでなく、家族や周りの人のためにも大切な制度です。40歳を過ぎると介護保険料を支払うことになりますが、それは将来の安心につながる「備え」でもあります。
制度の仕組みを知っておくことで、いざというときに慌てずに対応できるようになります。ぜひこの機会に、介護保険について少しだけでも理解を深めてみてくださいね。
あとがき
現場経験の中で、”初めて介護保険を申請する”方と接する機会が多々ありますが、大半の方は「自分が歳を取ったことを認めないといけない気がするから使いたくない。」、「まだ自分には必要ない」と仰られる方が非常に多い印象です。ですが、実際に認定を受け、サービスを使った後は「もっと早く使っておくべきだった」とほとんどの方が言われます。
介護保険を自分が使うことに抵抗がある方が多いように思います。
介護が必要な状態になったときには、ためらわずに活用してこそその価値が生きるのです。
“使うこと”は決して遠慮すべきことではなく、これまでの積み重ねに対する正当な権利なのです。
何から動いたら良いかわからない方は、スマホやパソコンで「地域包括支援センター・お住まいの住所」を入力し、お住まいの地区を管轄されている地域包括支援センター(あんしんすこやかセンター)に相談してみましょう。
筆者に直接聞く!という方はお問い合わせフォームからお問い合わせくださいませ