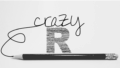こんにちは、KAIGO KAKUMEIです。今回は”2025年問題”と”2040年問題”について執筆しました。
みなさんは”2025年問題”・”2040年問題”をご存じでしょうか。日本は超高齢化社会となり、2025年時点で要介護者数は約720万人、2040年には約988万人にまで増えると言われています。
高齢化率が今後もどんどん高まるのに、担い手の数は不足している。今後誰がどのように要介護者を支えていくかを、国民全体でしっかり議論・対策・実行を回していかなければなりません。ひっ迫した未来にならないように、可能な限り多くの日本人でこの問題に向き合う必要があります。
2025年問題ってなに?
「2025年問題」とは、団塊の世代(1947〜49年生まれ)が75歳以上の後期高齢者となることで、日本の高齢者人口が急増し、医療・介護・福祉の需要が爆発的に高まる社会的課題を指します。
この問題は、医療・介護の人材不足、財源の逼迫、地域格差など多くの構造的課題を含んでおり、2015年頃から「地域包括ケアシステム」の確立がその解決策として掲げられてきました。
地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で、医療・介護・予防・住まい・生活支援を一体的に受けられる体制のこと。市町村単位での整備が求められ、モデルケースの発表や議論が盛んに行われていました。
実際の達成状況と現場の肌感覚
私自身、2025年問題に向けて、各市町村が地域包括ケアシステムを確立することが当然の使命だと認識していました。私の記憶だと2015〜2018年頃には、介護業界で「地域包括ケア」は当たり前の言葉となり、多くの自治体が議論を重ね、モデルケースを公表する自治体もありました。ところが、コロナ禍の影響もあり(これがかなり大きかった)、「2025年問題」や「地域包括ケア」という言葉を耳にする機会が減少。2025年を迎えた今、その達成状況に触れる報道や行政発表などはほとんど見られず、まるで何事もなかったかのように「2040年問題」へと話題が移り変わってしまいました。
実際、地域によっては包括ケアの仕組みが形骸化し、連携や情報共有が十分に機能していないケースもあります。一部ではICTやAIの導入による効率化が進んできてはいますが、全国的な達成とは全く言えません。
なぜ2040年問題へ話題が移ったのか
2040年問題とは、団塊ジュニア世代(1971〜74年生まれ)が65歳以上となり、85歳以上人口も急増することで、医療・介護の複合的ニーズがさらに深刻化するという課題です。
加えて、団塊ジュニア世代は就職氷河期を経験し、非正規雇用が多く、生活困窮リスクも高い。つまり、介護の「量」だけでなく「質」や「生活支援」の体制整備がこれまで以上に求められる時代がやって来るのです。
厚労省は2024年に「2040年に向けたサービス提供体制等のあり方に関する中間とりまとめ」を公表し、地域の実情に応じた柔軟な体制整備や、複数事業者の協働・ICT活用などを提案しています。
しかし、2025年問題の検証や振り返りが十分に行われないまま、次の課題へと移行してしまったことに違和感を覚えざるを得ません。
2040年を迎えるまでにやるべきことは明確
2025年問題の未解決を踏まえ、2040年に向けて私たちがやるべきことは明確です。
- 地域包括ケアの再構築と深化
単なる制度設計ではなく、現場の声を反映した「使える仕組み」として再設計する必要があります。 - ICT・AIの積極的導入による業務効率化
IT格差を埋め、現場の負担を軽減することで、限られた人材でも質の高いケアを提供できる体制を整える。 ※しかしこれには、”AI等導入における補助金を国がケチらずに十分な予算を充てるのか”、”介護保険制度上の人員基準の緩和などの整備”等の問題がある - 多職種連携と地域資源の可視化
医療・介護・福祉が顔の見える関係でつながり、情報共有や支援の「面展開」を進める。 - 人材の取り込み・育成と定着支援
介護人材の確保は喫緊の課題。働きやすさやキャリア支援を含めた多角的なアプローチが必要です。 - 制度の検証と現場主導の提言
制度は現場の実態に即してこそ意味がある。達成状況の検証と、現場からの提言が制度設計に反映される仕組みが求められます。
まとめ:介護の未来は、振り返りと行動の先にある
2025年問題は、単なる通過点ではなく、介護の未来を考える上での重要な節目でした。
その達成状況を振り返ることなく2040年問題へと話題が移る現状には正直、強い違和感があります。
制度や政策は、現場の実態に根ざしてこそ意味を持ちます。
だからこそ、”何ができていて、何ができていないのか”を丁寧に検証し、”誰のための仕組みなのか”を問い直す必要があります。
2040年に向けた再出発は、2025年問題の振り返りから始まる。
その視点を持ち、理解し、行動を起こすことが、介護の未来に希望を観るための一歩になるでしょう。
あとがき
今回も最後まで読んでいただきありがとうございました。個人でなんとかできる問題じゃないからこそ、たくさんの人が現状を知り、興味を持つことが何よりも大切なのではないでしょうか。
お問い合わせがある方は、ホームページのCONTACTフォームもしくはInstagramのDMにてお願いいたします!